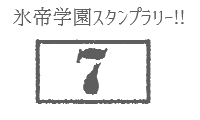「おまたせ!」
「あ、さーん!久しぶりッスー!」
急いで金券売り場に駆けつけると、そこにはお馴染みの立海メンバーがいた。
すぐさま私に気が付いて走り寄ってきてくれた切原氏の顔を見るのも久しぶりな気がする。
「さん、ゴメンね。呼び出して。」
「ううん!来てくれてありがとう!」
「おーっす、アレ?なんだよ衣装とかねーの?」
公式Tシャツとスカートの私を見て首を傾げる丸井君にギクっとする。
「え…えっと、うん、私は特にないんだー。」
「へー、でもそのTシャツもいい感じだな。」
丸井君の後ろから金券を買い終えたジャッカル君が顔を出した。
首から氷帝の公式ロゴタオルをかけている姿に胸がときめく。
「ジャッカル君、タオル買ったんだ!」
「おう、結構使えそうなサイズだったしな。」
「ピンク、すごく似合うよ!」
「そうか?サンキュ。」
「お前さんはピンクが似合わんな。」
「おわっ!び…っくりした、仁王君もいたんだ!」
「ずっとおったわ。」
ぬっと後ろから顔を近づける仁王君。
意外なことに仁王君もジャッカル君と同じようにタオルを購入したようで
キュっと首に結んでいた。なんだかおじいちゃんスタイルで可愛いね、と言うと気に障ったのか頭を叩かれた。
「さん、どこ行きます?俺、何か食いたい!」
「やっぱり食べ物だよね!じゃあ模擬店行こっか。」
「ありがとう、よろしくお願いします。」
隣ではしゃぐ切原氏、反対側には優しく微笑む幸村君。
……こ、このメンバーで歩くのはかなり注目を浴びそう。
現にさっき、金券売り場売り場の女の子が我先にと仁王君や丸井君に群がっているのを見た。
こんなメンバーの中に、1人ぽつんと魑魅魍魎みたいな私がいたら
悪目立ちするだろうな…。少し不安だけど、折角来てくれた友達に
そんなことを言うわけにはいかない。とにかく楽しんでもらえるように頑張ろう。
・
・
・
お昼前ということもあって、中庭は先程よりも随分人が多くなっていた。
少し気を抜くとはぐれてしまいそうな人混み。
昨日と同様、賑やかな客引きをするりとかわしながら、目的地へと皆を誘導する。
「えっと…スイーツ×スイーツってところを目指して歩いていくので、はぐれないようにしてね!」
「スイーツ!?お前、わかってんじゃーん!早く行こうぜ!」
予想通り、丸井君はスイーツの単語を聞いた途端目を爛々と輝かせていた。
ノリに任せてガシっと肩を組まれて、内心今日はラッキーデーだな、とか呑気に考えていた。
丸井君、男の子なのに良い匂いがする。
スイーツが好きだからスイーツの匂いが体からにじみ出ているのかな、なんて分析をしていると
ずいっと切原氏の手が私達を引き裂いた。
「ちょっと先輩!気安く触らないで下さいよ!」
「別にお前のもんじゃねぇだろぃ。」
「そ、そうッスけど、さんも嫌がってるじゃないッスか!」
「私は比較的ウェルカムな体制だから大丈夫だよ!」
「さんは黙ってて下さい!」
「あー、うるせーな。」
切原氏の気遣いを無駄にするような発言をしたのが気に障ったのか、睨まれてしまった。
微笑ましい言い合いをする2人を眺めていると、不意に手を引かれる。
振り向くと、キラキラオーラを放つ幸村君。人混みの中でも発光体のように光を放つその笑顔は、
見るだけで2歳ぐらい若返りそうな、神々しいものだった。
「さん、はぐれないように手を繋ごうか。」
「てっ…手!だ、だだ大丈夫!もう子供じゃないしそんな簡単にはぐれないよ!」
「ふふ、照れなくてもいいよ。」
有無を言わせずに私の手を握る幸村君に、心臓が天高く跳び出しそうになる。
い…いくら人混みだからとはいえ、結構大胆というか…いや、もしかして本当に
人混みで迷子にならないように、とか思ってるのかな…?
大きく掲げられた「スイーツ×スイーツ」の看板に向かってずんずんと歩いていく
幸村君の横顔は、久しぶりに見るからなのか一段とカッコ良く見えた。
刺さるような視線に気づいたのか、チラリとこちらを振り向いた幸村君が優しく笑う。
「っ…ご、ごめん。幸村君っていつどこで見ても輝くオーラを放ってるからつい見ちゃって…。」
「そうかな?さんなら大歓迎だよ。」
「…今日なんか幸村君ご機嫌だね?」
「……こういうイベント結構好きなんだ。ワクワクするよね。」
「そうなんだ!そっか…うん、氷帝学園祭は本当に楽しめると思うから、いっぱい見て回ろう!」
「それに、こうやってさんと2人で学園祭をまわるの楽しみにしてたしね。」
幸村君の脳内で約数名の人間が削除されている……。
あまりにも堂々と言い放つので、もしかして私がさっきまで見ていた人間は
霊界からの使者なのかと不安になる。思い切って振り向くと、
まだ賑やかに言い合いをしていた。大丈夫、現存してる。
しかし、この幸村君の笑顔は本当最高だな。ルーブル美術館に展示されてても、私不思議に思わないよ。
幸村君がテンション高い時ってこんなに殺傷能力高いんだ…!
いつも以上に優しい言葉で包み込んでくれる幸村君にトキめかないはずがない。
きっと今繋いでいる手は、どんどん熱くなっているに違いない。恥ずかしすぎる。
「なーーーーにが2人でまわるの楽しみにしてたんだ★ですか!俺達のこと忘れてません!?」
「………赤也、ごめん。忘れてたよ。」
「……赤也、お前の負けじゃ。相手が悪かったの。」
「っく…さん!俺だって!楽しみにしてたんスからね!ほら、寝不足でクマ!出来てるっしょ!」
「う、うん!今日も血行の良い可愛い顔だと思います!」
目元を見てくれと言わんばかりに、顔を近づける切原氏。
クマらしきものが全く見当たらないのが、また可愛い。
先輩に負けじと必死になる姿は、私の秘められた母性本能をざくざく掘り返していく。
氷帝にはいないタイプのアグレッシブな後輩ちゃんに、微笑ましい視線を送ると
それに気づいた切原氏がやっぱり不満げに頬を膨らませた。
・
・
・
「あ、ほら!着いたよ!」
「…へぇ、いい匂いがするね。」
「うっわ、全部美味そう!迷うな、これ!」
今年の激戦模擬店部門を制した、驚異の2年生集団。
スイーツ×スイーツはとにかく「本物感」がスゴイと噂だった。
店頭にデカデカと設置された簡易ショーケース。その中に
綺麗に並ぶ商品を見ると、確かに1位を取ってもおかしくないと思えた。
美味しそうなスイートポテトや、手作りシフォンケーキ、
そして店の奥でパティシエの調理服を着用した生徒たちが
クレープを作ったり、ケーキのデコレーションをしていたり…。
今までの学園祭の中でも、ここまで本格的なものは珍しいと思う。
聞けば、生徒の中の一人がパティシエの息子で将来は家を継ぐために
毎日家で修業をしているそうだ。
もちろん味だけではなく、呼び込みも上手い。
あえて大きな声で呼び込みまくるのではなく、
さりげなく店の前で立ち止まったお客様にメニューを渡して
自然と列に並ばせる。どの模擬店よりも綺麗に整列している待機列には
ご丁寧に列を区切るロープまで設置されている。
まるで本当の人気スイーツ店のような繁盛具合に、
中庭にいるお客様の注目も自然と集まる。
全員が真っ白で清潔感のあるパティシエ服を着ているのも目立つ理由だろう。
「…本格的だねー、どれにしようかな…。」
「マジかよ、このプチケーキが100円!?安すぎだろぃ!」
「ブン太、程々にしとかねぇと金券すぐ無くなんぞ。」
「そん時はよろしく、ジャッカル。」
「なんでだよ!」
「このシュークリーム美味そうじゃな。」
「仁王君、シュークリーム好きだね。合宿の時も食べてたよね?」
「……よう覚えとるな。」
「まぁね。私、氷帝のブレーンになろうと思ってるからデータ集めてるんだ。」
「…お前さんが?」
「うん!ほら、青学には乾君。立海には柳君がいるでしょ?氷帝には、この私が就任したいなと思って!」
「っぷ、無理じゃ諦めんしゃい。」
「な…そんなのわからないじゃん!」
待機列に並びながら、後ろにいた仁王君と何気なく話をする。
私の発言が何故か、随分ツボだったらしくずっとお腹を抱えて笑っている、失礼すぎるだろ…!
誰にも打ち明けていなかった密かな決意表明をバカにしやがって…!
取り敢えず今までの成果を伝えて納得してもらおうと、
データノートがわりの携帯を開くと、不意に仁王君が私の頬を包むように手で触れた。
「おわっ!…っな、ななな何?蚊?刺されてた?!」
「…っぷ…フッ…だからこのぐらいで動揺してるようじゃいつまでたってもあの2人のようにはなれん。」
「そっ…そそそそんなこと関係ないもん!」
「お前さんにはお前さんの出来ることがあるじゃろ。」
「…………例えば?」
「…………………まぁいずれ見つか「せめて1個ぐらい何か言ってよ!傷つくわ!」
「仁王、あんまりさんをイジめちゃ可哀想だよ。」
「…よう言うわ、誰よりもイジめるんが趣味の癖してのぉ。」
「ヤダな、人聞きの悪いこと言うなよ。」
クスクスと笑いあう仁王君と幸村君に挟まれて、私の脳内は桃源郷へとトリップしていた。
こういう風に大人数でいても、いつも誰からも構われないし、気にも止められないのが氷帝テニス部での私…。
でも今はっきりとわかる、やっぱり…やっぱり私の本来の居場所はきっと立海なのかもしれない…!
今まで何度も思い描いたバラ色の未来を思わず妄想してしまい、顔がニヤける。
…まだたったの数十分だけど、立海の皆と過ごすことで
どんどん私の中に秘められた女性ホルモン的なものが分泌されている気がする。
「いらっしゃいませ!お待たせいたしました!」
「やっときたかー!まずは、このプチケーキ5種類とも全部な!あと、チョコプリンとスフレチーズケーキと…
あー…でも、いや…よし、やっぱいちごプリンも買う!」
「明らかに食い過ぎだ、ブン太。」
「だってこれだけ買っても800円だぜ?お買い得すぎだろぃ?」
ついに私たちの順番がまわってきた。
我先にと丸井君がレジに飛びつく。
予想外の注文量に慌てたのか、女の子は必死にメモを取りつつ
ケーキを箱につめる係の子達にオーダーを叫び、伝えていた。
「丸井君、本当にスイーツ好きなんだね。」
「まぁ、氷帝の学園祭ってのがどんなもんかちょっとした小手調べみたいなもんだよ。」
パチンとウインクを飛ばす丸井君に腰が抜けそうになった。
…あ、相変わらず自分の魅せ方をよく理解してるなこの子は…!
うちのテニス部にはいないタイプの、親しみやすいイケメンボーイ。絶妙な垢抜け感にちょっとドキドキしてしまう。
きっと丸井君もがっくんと同じで天然培養のアイドルタイプだと思う。
・
・
・
「……マジで美味すぎるだろぃ…。」
「本当、素人が作ったとは思えない出来だな。」
「あ。あのクラスには将来パティシエ目指してる子がいるからね、本格的だって昨日から評判だったんだよ。」
「ふーん…このシュークリームも中々のもんじゃ。」
「ズルイっすよ、仁王先輩!最後の1個だったのに、可愛い後輩に譲ってくれてもいいじゃないッスか!」
それぞれが手にしたスイーツに、絶賛の声が寄せられる。
私は何もしてないんだけど、なんだかそれが誇らしくてついニヤけてしまう。
学園祭中の穴場スポット、中庭から少しはずれたところにある屋外ベンチで
私達は優雅なおやつタイムを過ごしていた。
「ごめんね、切原氏…。私もまさかあのタイミングで品切れになるとは思わず…!良かったらこれ、いる?」
ジャッカル君、私、そして仁王君がシュークリームを購入したところ
そこで丁度品切れになってしまい、最後尾に並んでいた切原氏は購入できなかった。
もちろんその場で散々ゴネていた切原氏だったけど、次のシュークリームが追加されるのは1時間後。
仕方なくアップルパイを頬張りながら、恨めしそうな顔をしていた。
「マジッスかー!さすがさん、優しい!」
「ふふ、きっと美味しいと思うから食べてみて。まだ口付けてないから。」
「へへっ!じゃ、早速いっただっき「俺も欲しかったのになぁ。」
向かいの席でうなだれる切原氏に、シュークリームを手渡そうとした時。
隣から、柔らかだけど妙に緊張感のある声が聞こえた。
私も切原氏もピタっと動作が止まる。
特に合図をするでもなく、私たちの視線は自然と発言者へと向けられた。
「…いいなぁ、赤也だけ。」
「ゆ、幸村君も欲しかったの…?」
「ぶっ、部長はブルーベリータルトだけでいいって言ってたじゃないッスか!」
「今、欲しくなったんだよ。俺だって心変わりぐらいするさ。」
「そんなのあんまりッスよ!俺がシュークリーム欲しいって駄々捏ねてた時、
最後にゲンコツ食らわせてまで黙らせたじゃないッスか!」
そうなのだ。
切原氏が、あまりに駄々を捏ねて仕舞にはレジ係の女の子に
今すぐシュークリームを出さないと暴れるぞと、犯罪スレスレの脅しを始めたところに
ニコニコ笑顔の幸村君がやってきて、常日頃から跡部の暴力を全身で受け止めている私ですら
軽く引くレベルの、脳天直撃ゲンコツをお見舞いしていたのを見た。
アレだけ騒いでいた切原氏がガチでちょっと涙目になっているのを見て、立海の知られざる闇を垣間見た気がした。
「ま、まぁまぁ…。幸村君も欲しかったならまた後で行ってみたらいいよ!その頃には新しいの出来てるだろうし!」
「そ、そうッスよ!また行けばいいじゃないッスか!」
「ふーん…、さんも赤也の味方なんだね。」
「え?!いや、味方とかそういうのじゃないけど…。」
「次は幸村君が駄々捏ねだしたぞ、ジャッカル。」
「…仕方ねぇな、ほら幸村。やるよ、俺のシュークリーム。」
苦笑いしながら、何のためらいも無く己のシュークリームを差し出すジャッカル君、本当カッコイイ。
こんなに懐の深い同級生がいる世界って、一体どんな天国なんだろう…。
つい癖で、氷帝での生活と比較してしまう。だけど、きっとジャッカル君が同じテニス部にいたなら、
私は今より約5倍ぐらい優しい気持ちに溢れた女の子になれていたと思う。
「いらない。」
「いらねぇのかよ!」
しばらくジャッカル君の手元のシュークリームを見つめた幸村君が、
プイっと顔を逸らす。ジャッカル君の素早いつっこみに思わず笑ってしまった。
「さんがくれるシュークリームが欲しい。」
「な、何なんスかそれ!」
「…じゃあ、ほらよ、赤也。お前にこれやるから、は幸村にあげてやってくれ。」
「スゴイね、ジャッカル。この一瞬で俺もさんも皆がwin-winになれる解答を導き出せるなんて。」
「どっこがwin-winなんスか!そんなの何か…なんか嫌だ!俺だってさんのシュークリーム欲しい!」
「わがまま言うなよ、赤也ー。シュークリームはどれも同じだろぃ。」
「可哀想じゃが、お前さんが諦めたほうが話がはよ収まる。大人になりんしゃい、赤也。」
「いやだいやだいやだ!なんで…っ、なんで俺が1番年下なのに全然優しくしてくれないんスか!そんなの幸村部長が我慢すればいいじゃないッスか!」
なんか…なんかよくわからない内に切原氏が諦めろ的な空気になっているのが怖すぎる…
決して大きな声で威嚇しているわけでもなく、ただただほほ笑んでいるだけの幸村君。
あの俺様人間跡部ですら首を傾げるぐらい、幸村君の言ってることは滅茶苦茶すぎるのに、不思議と逆らえない雰囲気がある。
切原氏が不憫すぎて涙がでそう。
…でも、ここは収集をつけるためにも…おこがましいかもしれないけど、なんとか私も頑張らないと…!
誰からも必要とされなかった哀しきジャッカル君のシュークリームは
既にジャッカル君によって食べられ始められちゃってるし…!私の手の中のシュークリームもそろそろ溶け始めそうだし…。
「あっ…あのー…先に私があげるって約束したのは、その切原氏なので…やっぱり切原氏にあげようと思います。」
「……っさん…!!」
「ごめん、幸村君!ちゃんと後で埋め合わせはするからさ!」
思い切って切原氏にシュークリームを手渡し、誠心誠意幸村君に頭を下げる。
四面楚歌状態からのまさかの大逆転に、普通に泣き出しそうな切原氏。…君も…苦労してるんだね…。
自分で下した判断ながらも、やっぱり幸村君の顔色が気になる私は
恐る恐る彼の顔を覗いてみた。だけど、特に怒っているような様子も無く変わらぬ笑顔。
取り敢えず収まったと、ホっと胸をなで下ろしたところに後ろから猛烈に肩を叩かれた。
「…あーあ、お前考えうる限り最も最悪な選択肢をチョイスしたぞ、今。」
「幸村はアレで案外根に持つタイプじゃからのぉ。」
「えっ!い、いや…え、でも私は公正な判断を…!」
ひそひそと私に耳打ちしたのは、仁王君と丸井君だった。
え…そんな、声を出すのも憚られるジャッジだったかな…?
だって、普通に切原氏が可哀想で…なんだか氷帝の中での私の扱いに似ている部分があって同情しちゃったというか…。
「お前さぁ、幸村君に理屈が通じると思う?」
「通じないの!?」
「…見てみんしゃい、あの顔。お前さんが赤也を選んだことで、怒りの矛先がまっすぐに赤也に向かっとる。」
「…ああ見えて、幸村って結構子供だからな。」
パクっとシュークリームの最後の一口を食べ終えたジャッカル君がポンポンと慰めるように私の肩を叩いた。
そ…っそんな…!良かれと思って出した助け舟が、余計に切原氏を苦しめる結果に…!?
こそこそと話をしている私たちを見ることも無く、手にしたシュークリームをキラキラとした目で見つめる切原氏。
それを笑顔で見守っているように見える幸村君……ほ、本当に怒ってるのか?あれで…。
「さん、俺…嬉しいッス!いただきます!」
「…今、突然頭上からそのシュークリームに鳥の糞が落ちればいいのに。」
「なっ、何言うんスか!やめてくださいよ!」
「へぇ、随分強気だね。やっぱり自分はさんに選ばれたんだっていう選民意識から俺に対してもそんなに偉そうになっちゃうのかな?」
「別に偉そうにとか…してないッス!」
「こんな結果になるぐらいだったら、俺も赤也みたいに駄々を捏ねておけばよかった。
さん自身がシュークリームを食べたいから買ったんだろうし…俺も欲しかったけど、さんの気持ちを優先したのが今となっては悔やまれるよ。」
「っぐ…!」
「さ、早く食べなよ赤也。いかにもさんが好きそうな年下っぽい可愛い振る舞いで、俺から無理矢理勝ち取ったそのシュークリームをね。」
「…………さん、ごめ…ごめんなさい!俺そんなつもりじゃ…!」
2人の会話を無言で見守っていた私達。
既に一口かぶりついたシュークリームを見つめながら、心底申し訳なさそうな顔で震える切原氏。
…きっと、全員腹の中で感じていることは1つだと思う。
幸村君……、大人げなさすぎるよ…!!